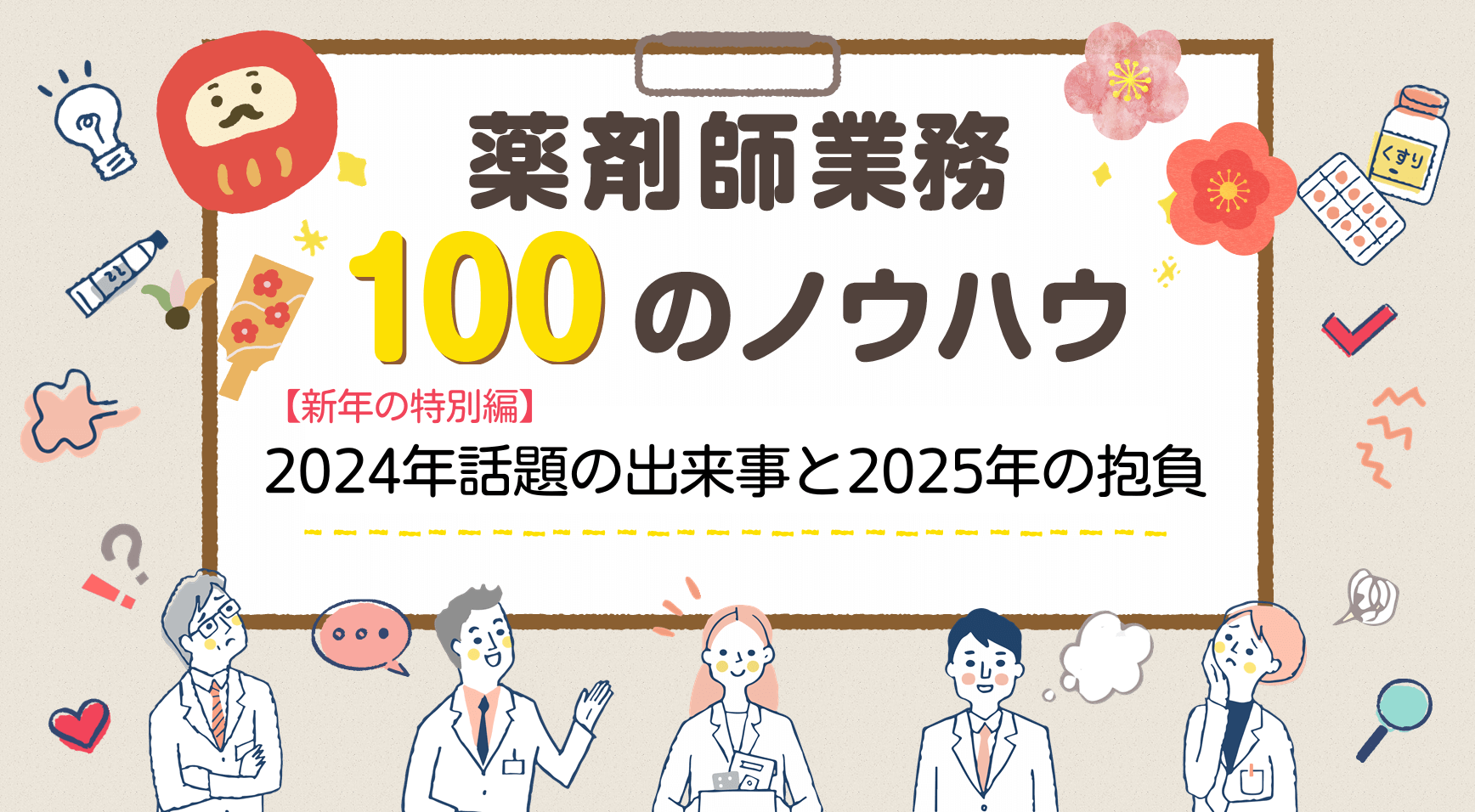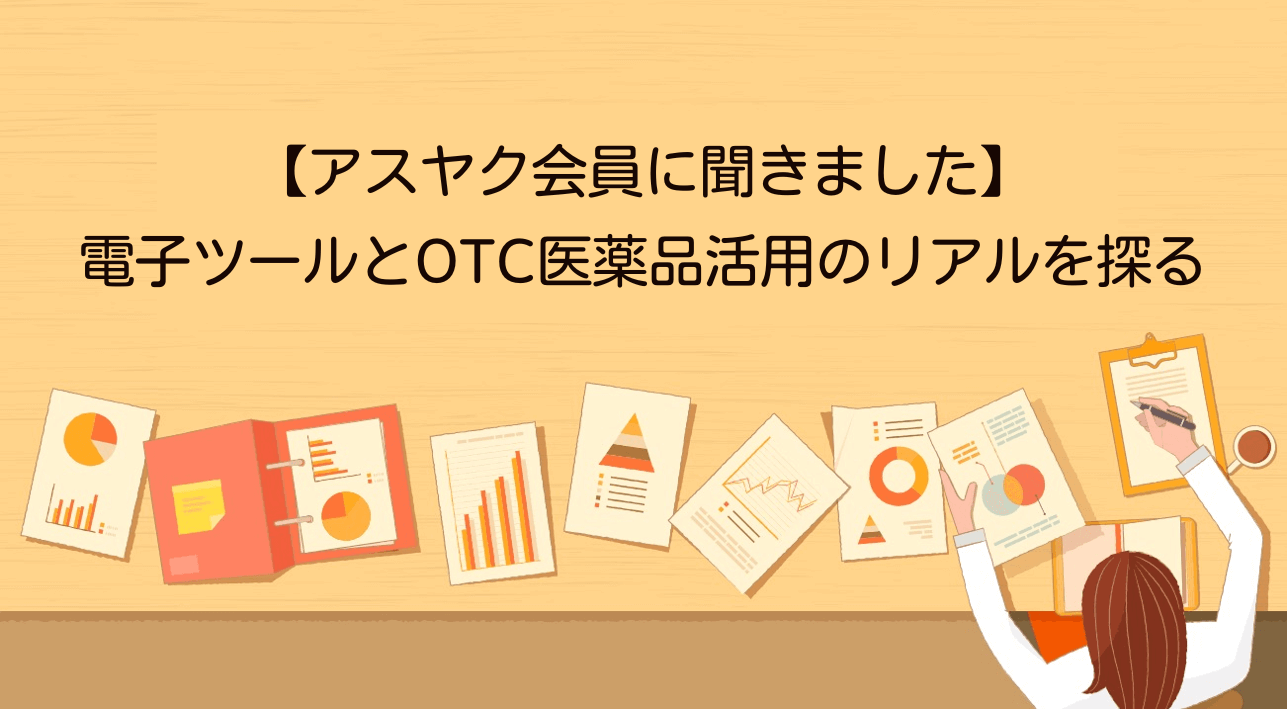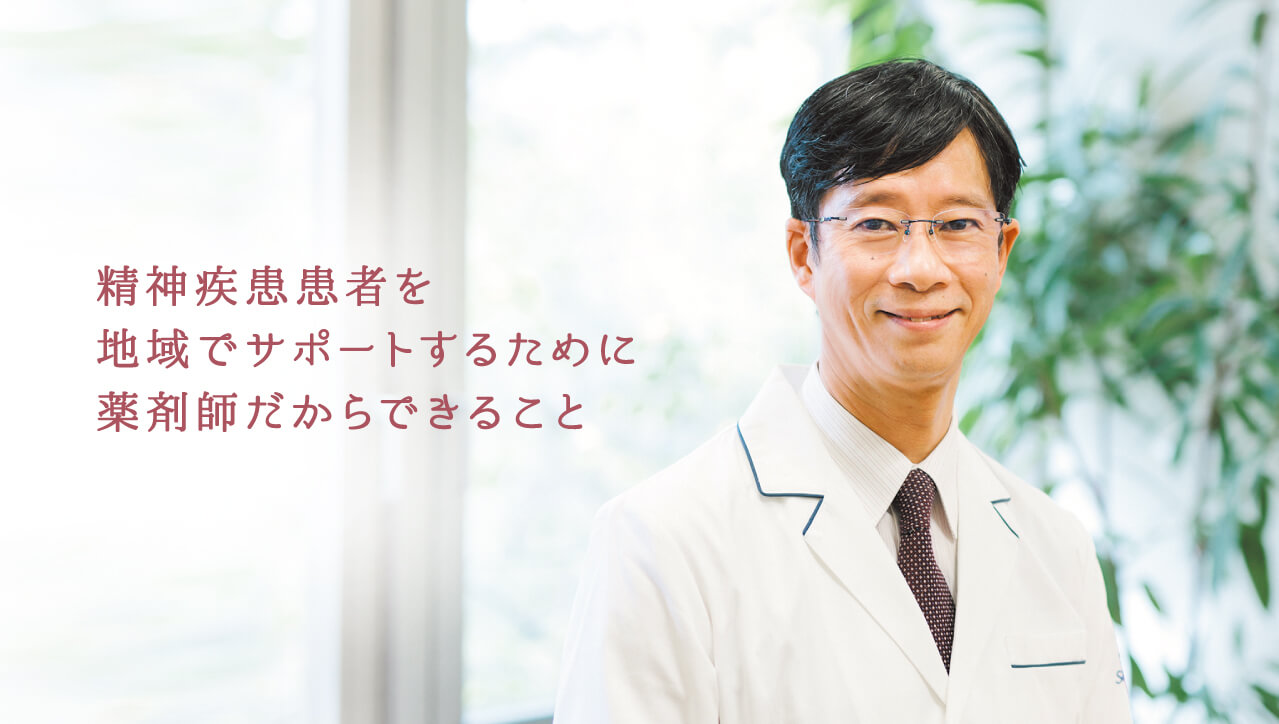
成井 繁 先生
日本精神薬学会会員(評議員)、日本在宅薬学会会員、日本医療薬学会会員、日本臨床精神神経薬理学会会員、日本地域薬局薬学会会員:日本精神薬学会 認定薬剤師、日本病院薬剤師会認定 精神科薬物療法認定薬剤師、漢方薬・生薬認定薬剤師、認定実務実習指導薬剤師、日本アンチドーピング機構認定 スポーツファーマシスト
(2020年8月取材)
近年、精神疾患患者を地域全体でサポートしていこうという動きが活発化しています。厚生労働省からも「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の指針が発表されましたが、これにより薬剤師の役割はどのように変わっていくのでしょうか。
精神科薬物療法認定薬剤師であるあおぞら薬局 藤沢店の成井繁先生にお話を伺いました。
(本記事は医薬情報おまとめ便内、特集企画「5大疾病の現状と薬剤師の関わり方」にて掲載した記事です。 )
精神疾患患者の背景を理解して
社会の一員として生活ができるサポートを
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とは、2017年に厚生労働省から発表された精神疾患患者に関する新しい理念です。これは、従来の「地域包括ケアシステム」から一歩踏み込み、高齢者に限らず精神障害者についても地域が一体となってサポートしていきましょうという考え方。皆さんにも、この取り組みが始まった背景を知ってほしいと思います。
日本の精神疾患の患者さんは特に認知症や気分障害の方が増え続け、現在419万人を超えています。このうち9割以上の方が、外来治療で保険薬局に足を運び、治療しながらも社会の一員として自分らしく暮らしたいという思いをもっています。
一方、入院している患者さんに目を向けると、約6割が1年以上の長期入院となっており、「住居や支援がない」という理由で退院できずにいる患者さんも3割以上もいらっしゃいます。また、たとえ退院しても「服薬の援助が受けられない」「日常生活に強いストレスを感じる」などの理由で約4割が1年以内に再入院するという現実もあります。いま、多くの精神疾患の患者さんが、社会の支援を必要としているのです。