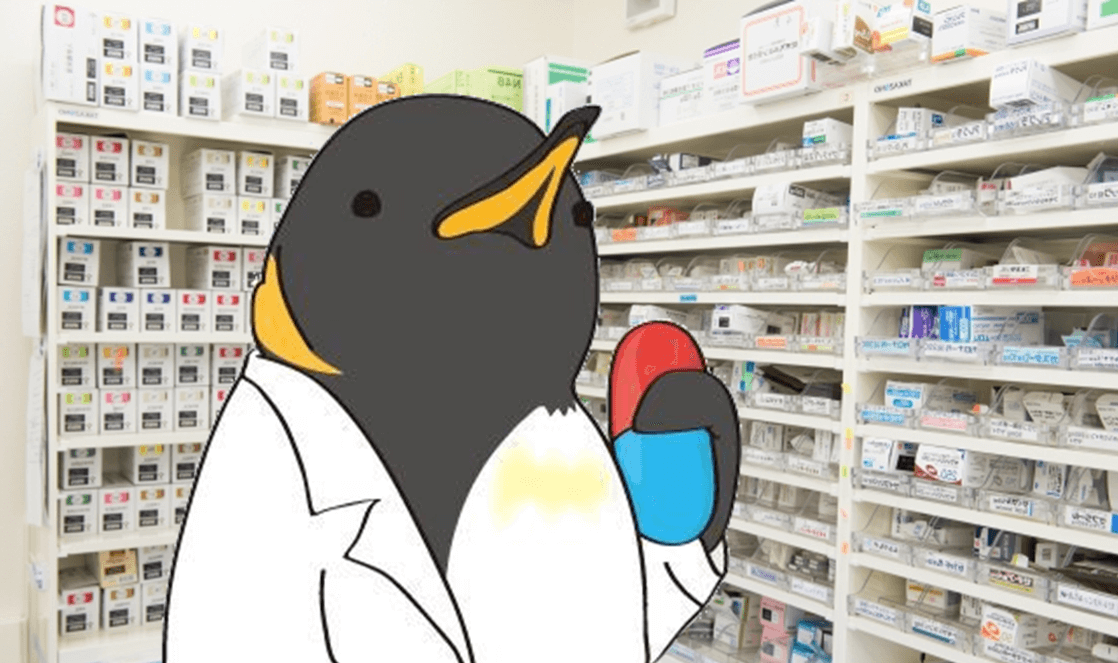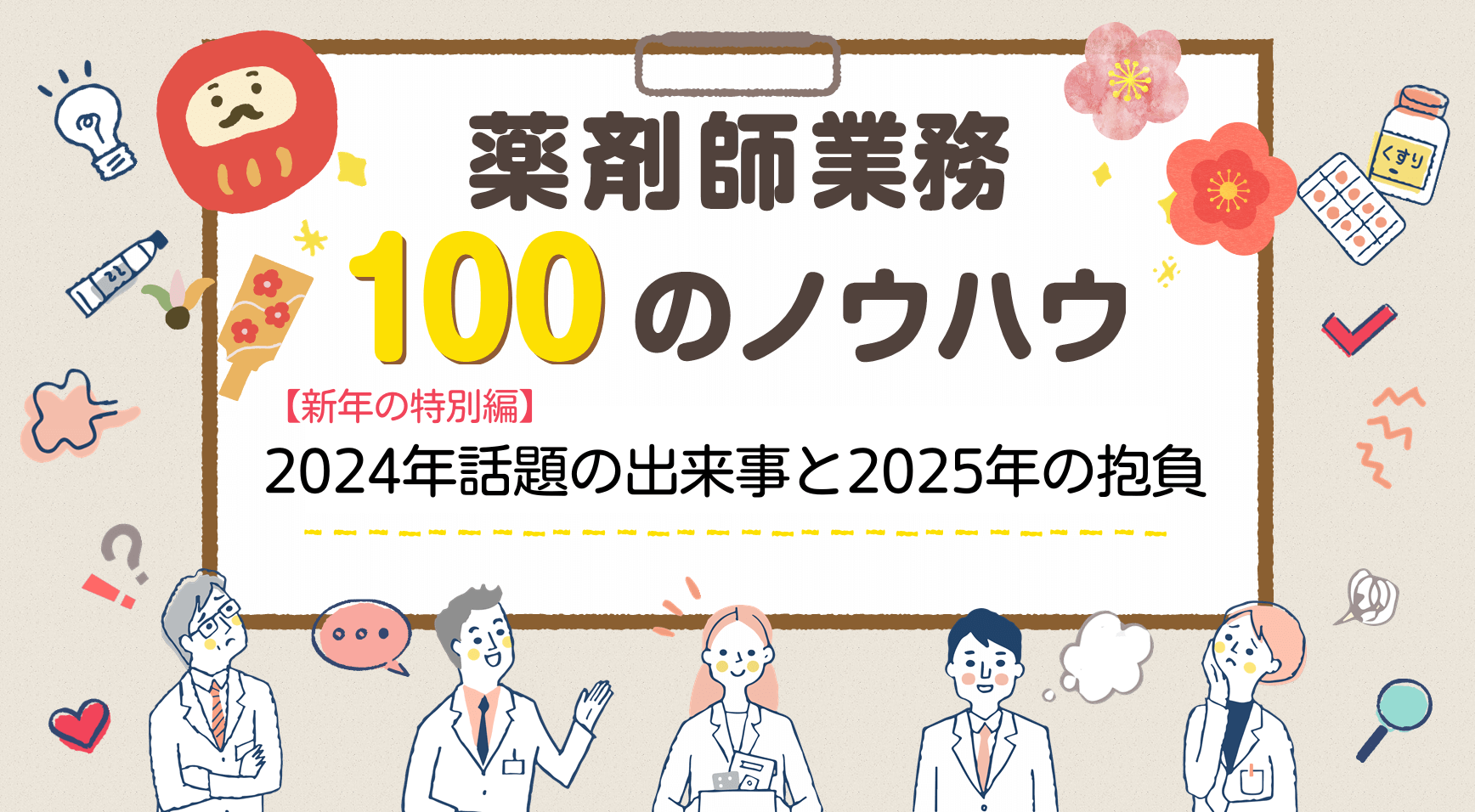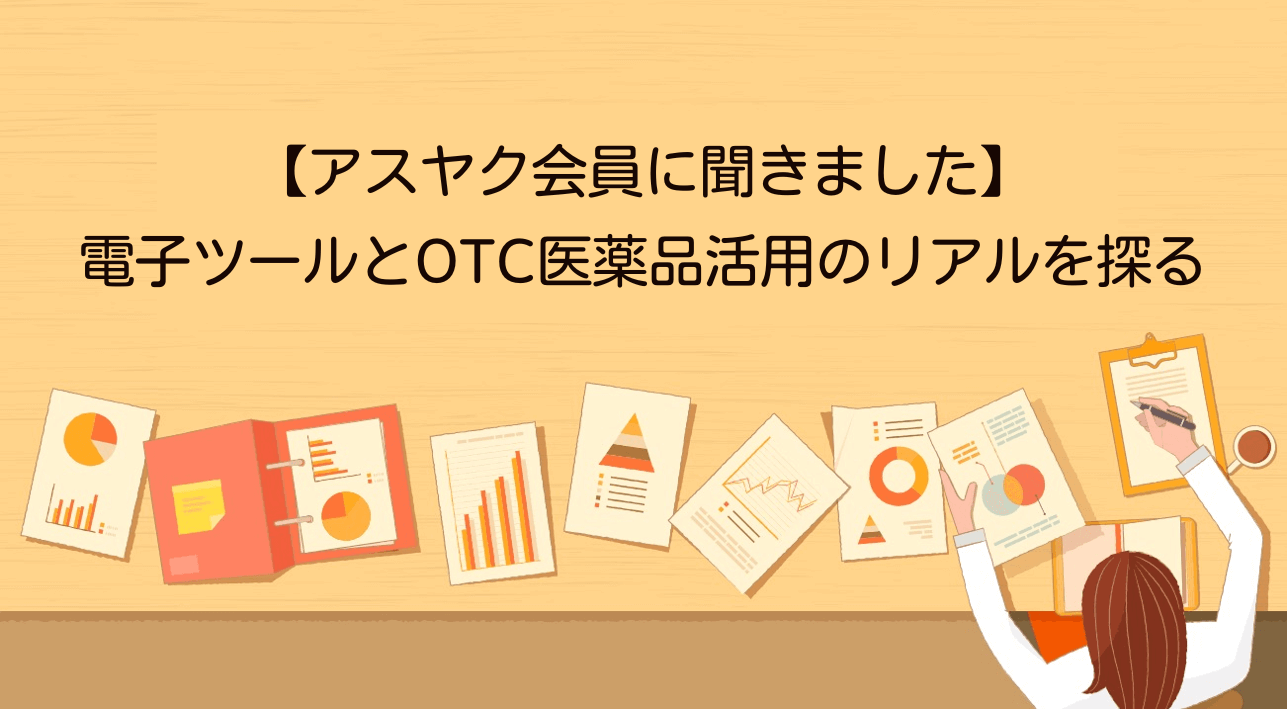1)地域包括ケアの実践と在宅医療の普及と啓発 ~退院支援とのつながり~
こだわりを持って取り組んでいることは3つあります。
まず一つ目は、「地域包括ケアの実践と在宅医療の普及と啓発」です。薬局時代に在宅医療に関わった経験と病院で行なっている退院支援がつながっていることを確信したため、その中身とノウハウを普及・啓発していきたいと思ったわけです。
在宅医療では、医師、看護師、ケアマネジャーらと連携して、在宅療養生活の再構築、維持そして向上のために医療と介護の両面から支援をしていきます。薬剤師による服薬支援は在宅生活の維持につながり、結果としてケアプランにある目標の達成にも寄与します。
退院支援も同じです。病棟でのカンファレンスでは退院後の在宅療養生活を想定した話し合いがなされます。それぞれの専門職が患者個々の目標達成のために必要な事項についてコンサルテーションします。薬剤師は、自宅に戻った後も服薬が継続できる服薬支援方法(後記)を入院中から考えます。その際、支援者の選定も同時に考えます。支援者は家族、ヘルパー、訪問看護、そして薬局薬剤師など様々です。かかりつけ薬剤師の名前が薬手帳に記載されていれば、退院前から連絡を取り合うことも大切です。
以上の通り、在宅医療と退院支援に関して、患者と家族を中心として、 連携した多職種で患者の療養を支援するのです。それが真の地域包括ケアにつながります。
多職種連携に苦手意識を感じている方は、まず訪問看護とケアマネジャーと情報を共有するところから始めてみてください。共有すべき最重要項目は、個々の患者さんの「思い、目標、在宅療養の目的」です。その目標や目的を共有し、その達成のために薬剤師として何をすればいいかを考えていけば、自然とチーム意識がみんなに芽生えます。達成したら共に喜びあえます。こ
れは在宅医療も退院支援も同じです。目標なき医療、看護、介護は無いのです。それを薬剤師は知らぬまま、ただひたすら調剤し、飲めるようにすることだけに傾注してきた時代が長く続いた結果、連携することがとんでもなくレベルの高いスキルのように感じているだけです。本当は当たり前のことなので、スキルなんて不要ですし、すぐに誰でもできます。 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(J-HOP)では、在宅訪問の基礎講座とともに、地域包括ケアへの関わり方もブロック研修会やメーリングを通して学び合っています。私もこの内容の普及と啓発には今後もこだわって関わっていこうと思います。ぜひ、皆さんもJ-HOPにご参加ください。