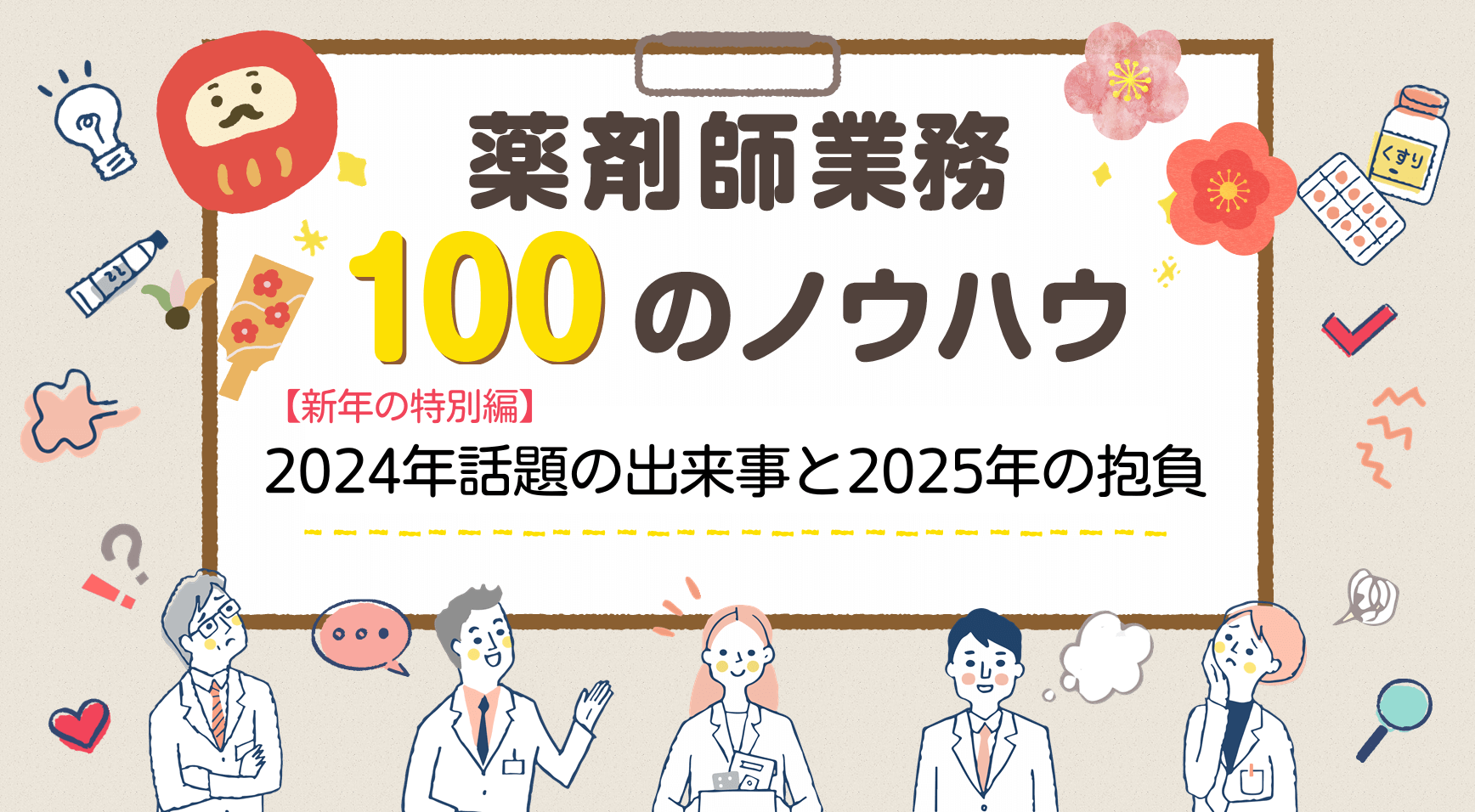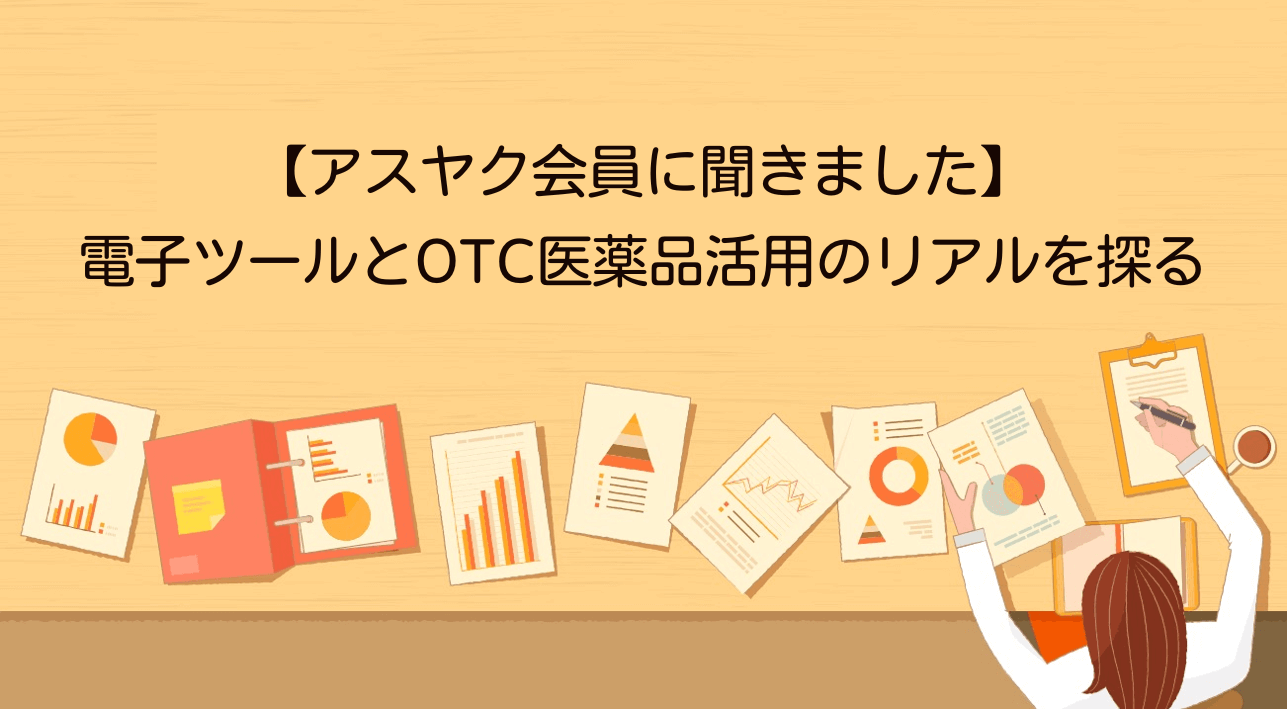日本大学医学部を卒業後、日本大学病院小児科、都立大塚病院小児科などで勤務。
森戸やすみをペンネームとして、小児の病気や育児に関する書籍を多数執筆している。
(2019年12月取材)
子どもやその親を取り巻く環境は、近年、大きく変化しています。共働きの家庭が増加し、スマホでの検索が当たり前になって……。医療情報の入手のしかたや、子と親が抱える悩みも少しずつ変わってきました。
現代の親子はどのような不安を抱え、どんなサポートを必要としているのか? 小児科医の松村有香先生にお聞きします。
共働きで情報感度が高く、
だからこそ不安を抱えがちな保護者が多い
小児科医になって23年。研修医だったときと現在とで、子どもがかかりやすい病気やその症状に大きな変化はないと感じています。もっとも大きく変わったのが子どもを連れてくる親御さん。1990年代に比べると働くお母さんの数は倍に増えました(※)。病院や薬局に来るお母さんの大半は“働いている”と思って接したほうがよいと思います。また以前に比べ、お父さんが連れてくることも多くなっています。しかも、子どもの体重やうんちの状態、食べたものなどをスラスラと答えられる。母親と同じような感覚・距離感でお子さんと関わっている父親が増えているなと思います。
もうひとつ、近年の親御さんの特徴だと感じるのが、ネットで情報収集をしてくるケースが多いところ。症状で検索して疑わしい病気を調べてから受診される方が増えました。なかには、うんちや蕁麻疹の状態をスマホで撮って診察時に見せてくれる方も。ICTを活用して上手に受診する親御さんが増えているように思います。
一方で、“調べすぎ”による弊害も。信頼性の低いWebサイトの情報を鵜呑みにして、過剰な不安を抱えて受診する親御さんも増えました。共働きで、情報感度が高く、だからこそ不安を抱えがち……。そんな方が最近の、比較的多い保護者像なのかなと思います。
※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「専業主婦世帯と共働き世帯」