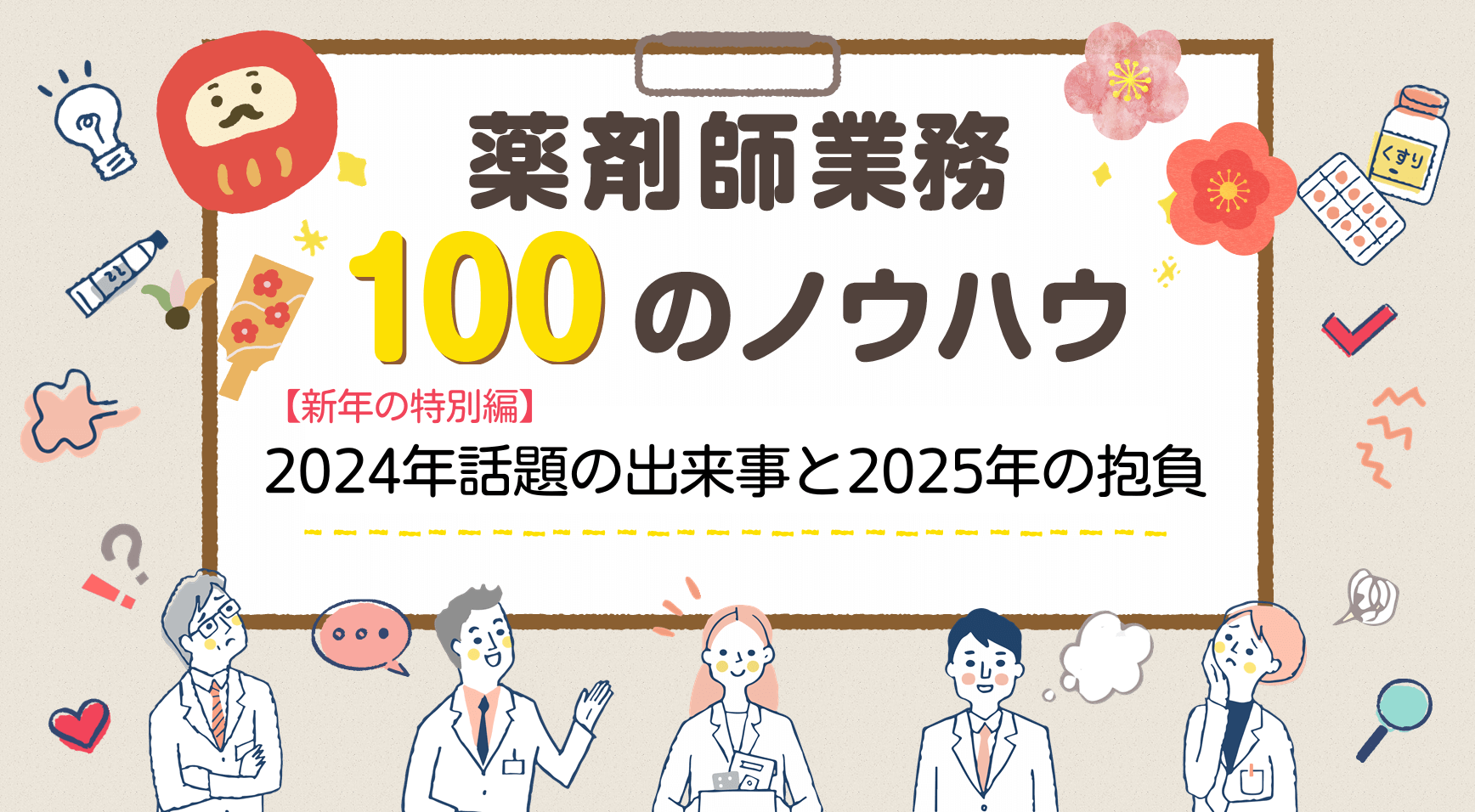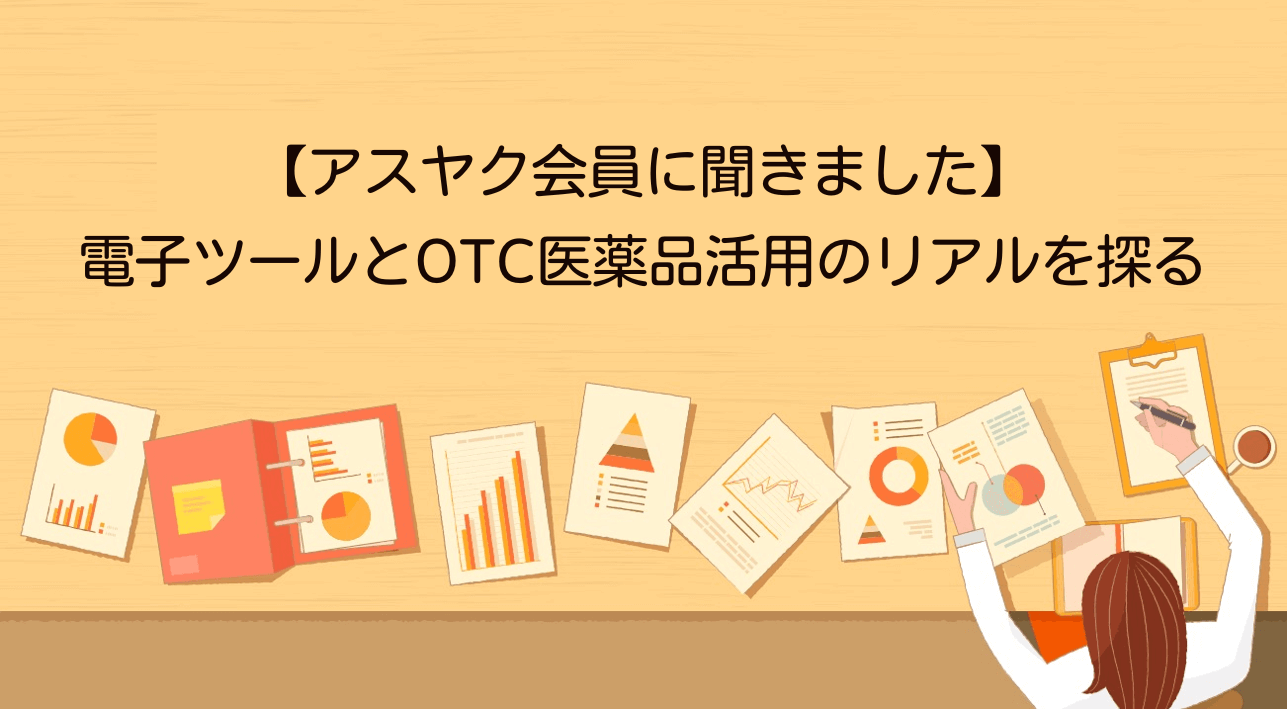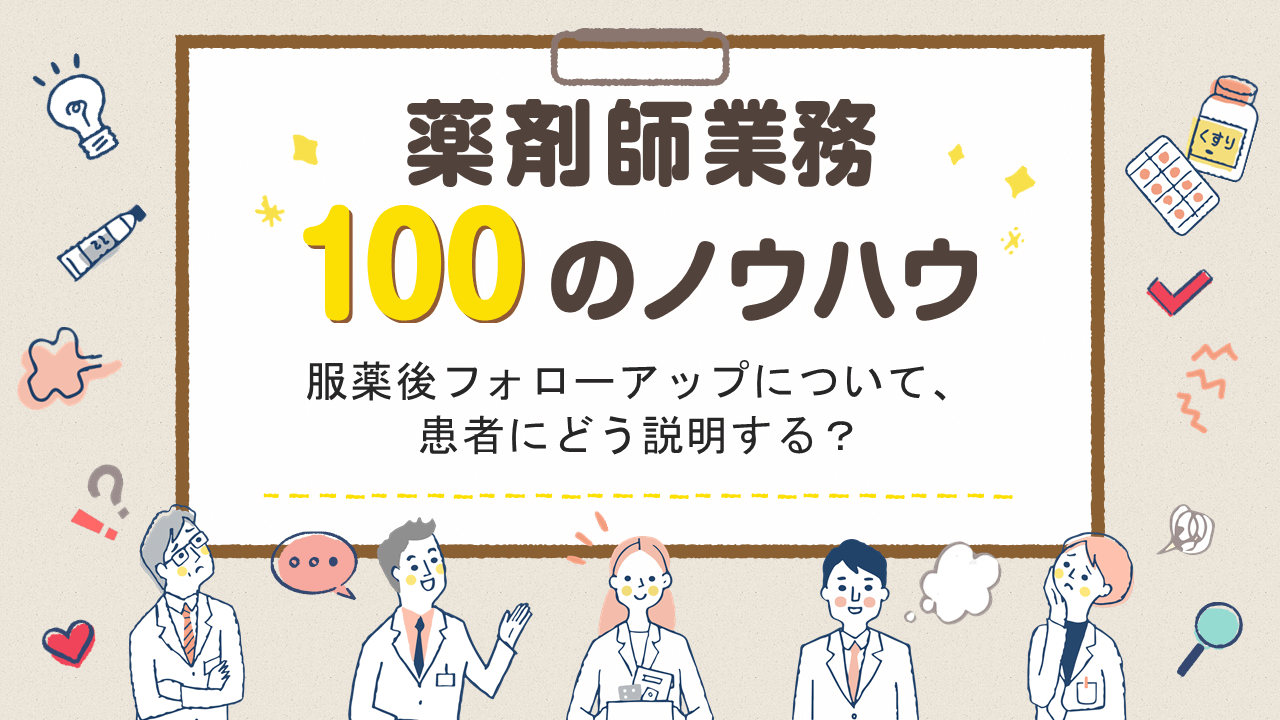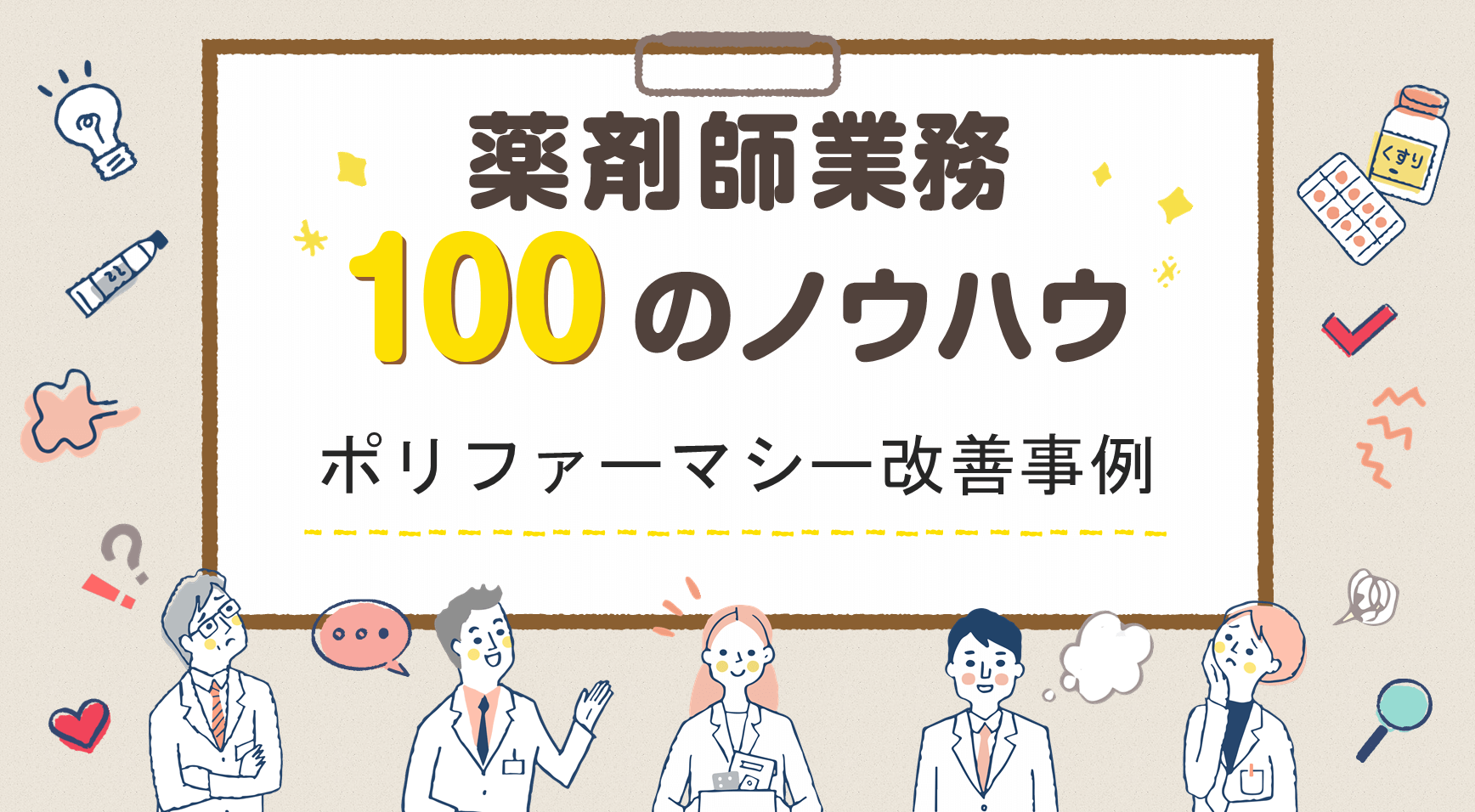2025年4月の診療報酬改定の見直しにより、「医療DX推進体制整備加算」におけるマイナ保険証の利用率要件がさらに厳格化。薬局でも“マイナ受付率”が実質的な評価指標となり、これまで以上に対策が求められています。
今回はアスヤク会員を対象に実施したアンケートをもとに、現場で実際に行われている取り組みを紹介します。
アンケート回答いただいた中から、今回は38のノウハウをピックアップしました。ぜひ自身で真似できそうな説明や取組を実施してみてください♪
| 実施時期 | 2025年4月 |
|---|---|
| サンプル数 | ネクスウェイ アスヤク会員 200名 |
| 手法 | WEBアンケート |
◆マイナ保険証の利用率を高めるための取組の実施の有無

マイナ保険証の利用率を高めるための取組を実施しているか、伺ったところ、
89.5%の方が「はい」と回答されていました。
一方で「いいえ」と回答された方には、「あまりにも患者が無反応なので、もう何もしていない。」「あまりマイナ保険証を勧めたいと思っていない」といった意見もありました。
◆取組の事例
「現在マイナ保険証の利用率を高めるために、実施している取組があれば教えてください。」という質問には、178名の回答をいただきました。

取組をカテゴリ別に分けると、約8割の方が「声かけ」を実施しているとのことでした。ポスターの掲示やチラシを配布する取組や、端末の操作説明などの対応をされている方もいらっしゃいましたが、少数に留まっています。
「発熱外来の患者が増えマイナ使用率が右肩下がりになってしまい、現状打開策が見いだせていない。」「声かけくらいしかできていないので、他薬局の取り組みを教えてほしい。」「声かけくらいしか出来ない。」といったお困りの声も寄せられました。
今回は、マイナ保険証の利用率を高めるための取組や工夫別に全38件のノウハウをご紹介します。
1.声かけ
- 使ってる・使ってない・持ってないを記録して、使ってる患者さんには毎回声かけをする
- マイナカード持ってこられない患者様には数か月に1回声かけしている。
- 月始めの患者さんに毎回マイナカードを持ってないか声かけしている。
- フォローアップ電話時にマイナ保険証持参のお願いを行う。
- 必ずマイナンバーカードの持参有無を確認、保険証が発行されなくなることを周知。
- 患者さんに声かけ。まだまだ勉強不足でわからないことが多くとりあえず端末にマイナンバーカードを通していただくことを求めている状態。
- 将来的に他の医療機関との医療情報が共有され、質の高い医療が受けられることを周知させています。
- 声かけと提示してもらった際の情報の活用方法などをお伝え。
- マイナンバーカード作成者に対する毎回の声かけ、作成していない人には作ったかの確認、電子薬歴にマイナンバーカードの状況を入力しています。
- とにかく日々の声かけ。利用する習慣がつけば、着実に利用率は上がっていきます。どうしても使いたくない人に勧めるのはクレームになるし、なかなか難しい。
- 全ての患者に持参の有無を確認している。 お薬手帳を持ってこない患者に投薬時に診療情報を活用している旨をお伝えしている。
- 来局患者全員への声かけ、マイナンバーカードの未作成患者に対しては、今後の必要性を説明 ・併用薬の多い患者が多いため、併用確認のために重要であることを説明。
- 声かけ、これしかないです。 してくれたらありがとうと伝える。
- 1度マイナ保険証を登録すると2回目以降はしなくて良いと勘違いされいる。こまめに声かけをしている。