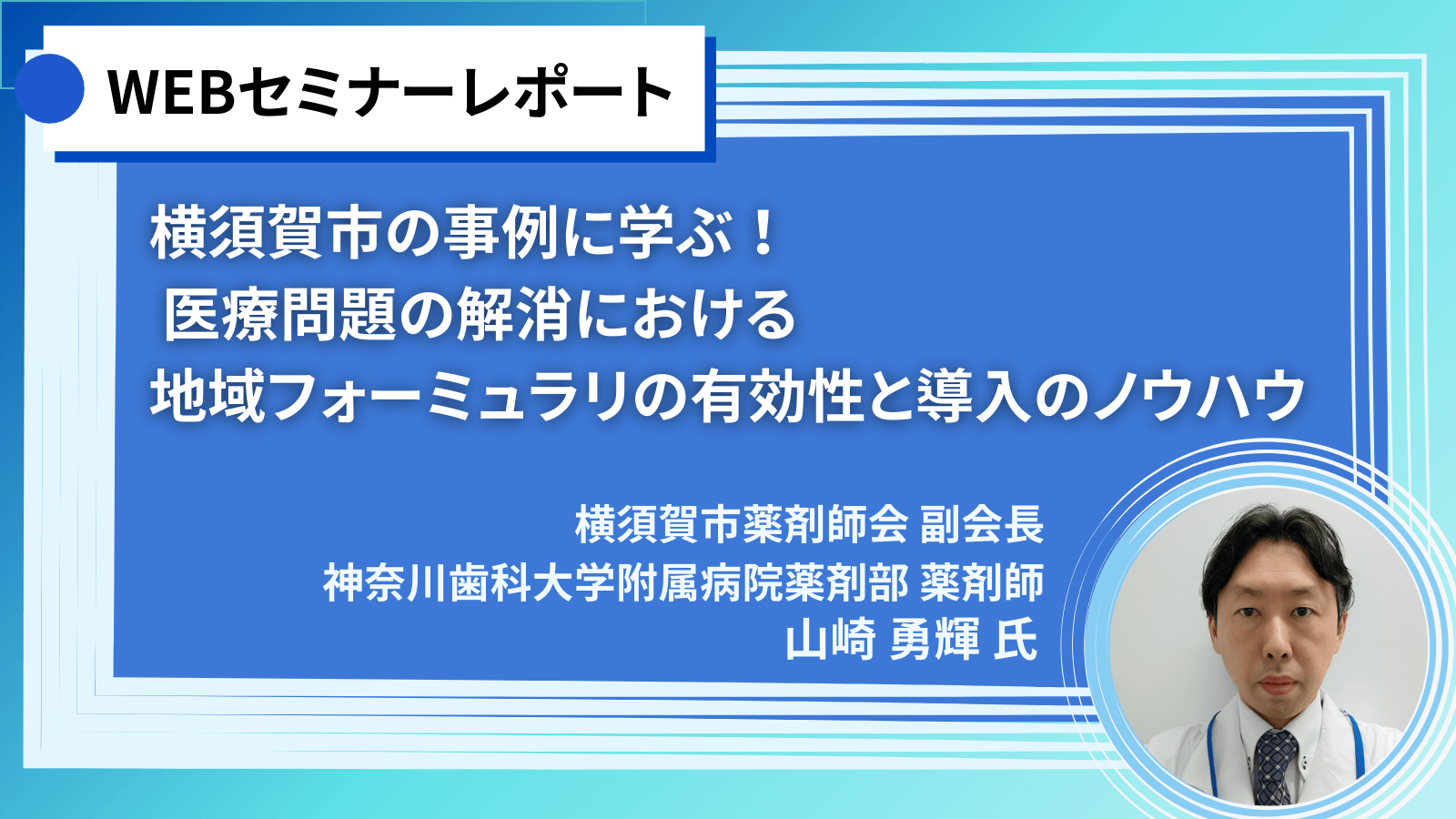
2025年1月28日、ネクスウェイはオンラインセミナー『医薬品適正使用と医療費適正化を目指した地域フォーミュラリの実態とは〜横須賀市薬剤師会における取り組み〜』を開催しました。講師として登壇してくださったのは、神奈川歯科大学附属病院薬剤部の薬剤師で、横須賀市薬剤師会の副会長を務める山崎勇輝氏です。
山崎氏は、横須賀市の事例を詳しく紹介しながら、地域フォーミュラリの導入から運用に至るまでの重要なポイントやノウハウを具体的に解説してくれました。
本記事では、そのセミナーから特に注目したい情報をピックアップしてレポートします。
残薬の大量発生、薬剤費を背景とした自己減薬
多様な問題を解決するカギは「シームレスな薬物療法」だった
セミナーでは、まず横須賀市が地域フォーミュラリを導入した経緯から紹介されました。さまざまな薬剤関連問題を解消する手立てを模索した結果、地域フォーミュラリの導入が効果的であるという結論に至ったといいます。
一定の効果を出した『ネイビーバッカープロジェクト』
山崎氏によると、横須賀市は以前から以下のような薬剤関連問題を抱えていたといいます。
・高齢化率30%を超える超高齢化社会。
・高齢者が多く、ポリファーマシーの問題を抱えている方が多い。
・在宅医療を受けている方、認知症の方も多く、それに伴いアドヒアランス不良や服薬管理不良の事例が数多く発生。
・結果的に残薬が大量に発生。
・薬物治療の質の低下や、医療費の圧迫といった問題につながっている。
こうした現状を受け、横須賀市の病院薬剤師と薬局薬剤師は、行政と協力して『ネイビーバッカープロジェクト』という残薬解消運動を展開。市民に専用のバッグを配布し、そこに残薬を入れてかかりつけ薬局へ提出してもらう仕組みです。
山崎氏は『ネイビーバッカープロジェクト』の意図について、次のように話します。
「医療者と患者さんが双方向でつながるプラットフォームを地域全体で構築し、残薬の『減少』ではなく『解消』を目指しました。また、薬の適正使用の推進やポリファーマシーの防止も狙いです」
そんな『ネイビーバッカープロジェクト』は、初年度から多くの残薬を削減することに成功します。しかし、以降は一定の効果は出るものの、成果は下げ止まりの状況が続いたそうです。

